新商品開発や事業戦略を考える際、顧客の潜在的な課題や技術の可能性をどのように捉えるかは企業の成長に直結します。
本記事では、ビジネスの根幹となるニーズ・シーズ・ウォンツの概念について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
これらの違いを理解することで、市場機会の発見から製品開発まで、より戦略的なアプローチが可能になります。

ニーズ・シーズ・ウォンツは、それぞれ異なる視点から市場や技術を捉える重要な概念です。
これらの理解は、効果的な商品開発の出発点となります。
ニーズ(Needs)とは、顧客が抱える問題や不満、改善したい状況を指します。
例えば、「通勤時間を短縮したい」「家事の負担を軽減したい」といった、生活や業務上の課題が該当します。
ニーズは往々にして顧客自身も明確に認識していない潜在的なものが多く、市場調査や観察を通じて発見されます。
シーズ(Seeds)は、企業が保有している技術や知識、リソースなどの「種」を意味します。
具体的には、特許技術、研究開発成果、製造ノウハウ、人材などが含まれます。
例えば、「高精度なセンサー技術」や「独自の材料加工技術」といった技術的な強みがシーズとなります。
ウォンツ(Wants)は、顧客が具体的に欲しいと思っている商品やサービスです。
ニーズが抽象的な課題であるのに対し、ウォンツは「最新のスマートフォンが欲しい」「おしゃれなカフェで働きたい」といった明確な欲求として表現されます。
ニーズとシーズの最大の違いは、市場起点か技術起点かという視点の違いにあります。
それぞれの特徴を理解することで、商品開発のアプローチを適切に選択できます。
ニーズは「顧客の課題解決」を出発点とするマーケット・インの発想です。
市場調査やユーザーインタビューを通じて顧客の困りごとを発見し、それを解決する商品を開発します。
例えば、高齢者の「薬の飲み忘れ」という課題から服薬管理アプリが生まれるケースがこれに該当します。
一方、シーズは「技術の活用可能性」から始まるプロダクト・アウトの考え方です。
企業が持つ優れた技術や知見を活かして、新たな市場や用途を開拓します。
具体的には、半導体技術を活用してスマートフォンから自動車まで幅広い分野に展開するケースが代表例です。
どちらのアプローチも成功例がありますが、市場の受容性と技術的実現可能性のバランスを取ることが重要です。
ニーズ重視では確実性は高いものの革新性に欠ける場合があり、シーズ重視では技術的に優れていても市場に受け入れられないリスクがあります。
ウォンツは、ニーズとシーズを橋渡しする重要な役割を担っています。
顧客の具体的な欲求として表現されるウォンツを理解することで、より効果的な商品開発が可能になります。
ニーズが「移動時間を有効活用したい」という抽象的な課題だとすると、ウォンツは「電車内でも快適に動画を視聴できるタブレットが欲しい」という具体的な欲求になります。
この関係性を理解することで、ニーズを満たすための具体的な解決策を提示できます。
シーズとウォンツの関係では、技術的な可能性と市場の要求をマッチングさせることが重要です。
例えば、AR技術(シーズ)と「より直感的なナビゲーション」(ウォンツ)を組み合わせることで、革新的な地図アプリが誕生します。
ウォンツを正確に把握することで、顧客の期待値と実際の商品機能のギャップを最小化できます。
また、ウォンツの変化を継続的に監視することで、市場トレンドの変化にも迅速に対応可能になります。
商品開発において、ニーズ志向とシーズ志向のどちらを選択するかは、企業の戦略や市場環境によって大きく異なります。
それぞれのアプローチには明確な特徴があり、適切な使い分けが成功の鍵となります。
| 項目 | ニーズ志向 | シーズ志向 |
|---|---|---|
| 市場確実性 | 高い | 不確実 |
| 技術革新性 | 限定的 | 高い |
| 競合優位性 | 一時的 | 持続的 |
| 開発リスク | 低い | 高い |
一方で、ニーズ志向は既存市場の改善に留まりがちで、革新的な商品が生まれにくいというデメリットがあります。
また、競合他社も同様のニーズに着目するため、差別化が困難になる場合があります。
シーズ志向は技術的優位性を活かした独自性の高い商品開発が可能です。
特許技術や独自ノウハウを基盤とするため、持続的な競争優位を構築できる可能性があります。
しかし、市場の受容性が不透明で、商品化までの時間とコストが膨大になるリスクがあります。
企業の置かれた状況や戦略目標に応じて、適切なアプローチを選択することが重要です。
安定的な収益確保を重視する場合はニーズ志向、長期的な競争優位性を目指す場合はシーズ志向が適しています。
多くの成功企業は、両方のアプローチを組み合わせて活用しています。
例えば、短期的な収益はニーズ志向の商品で確保しながら、中長期的な成長はシーズ志向の研究開発に投資するという戦略です。
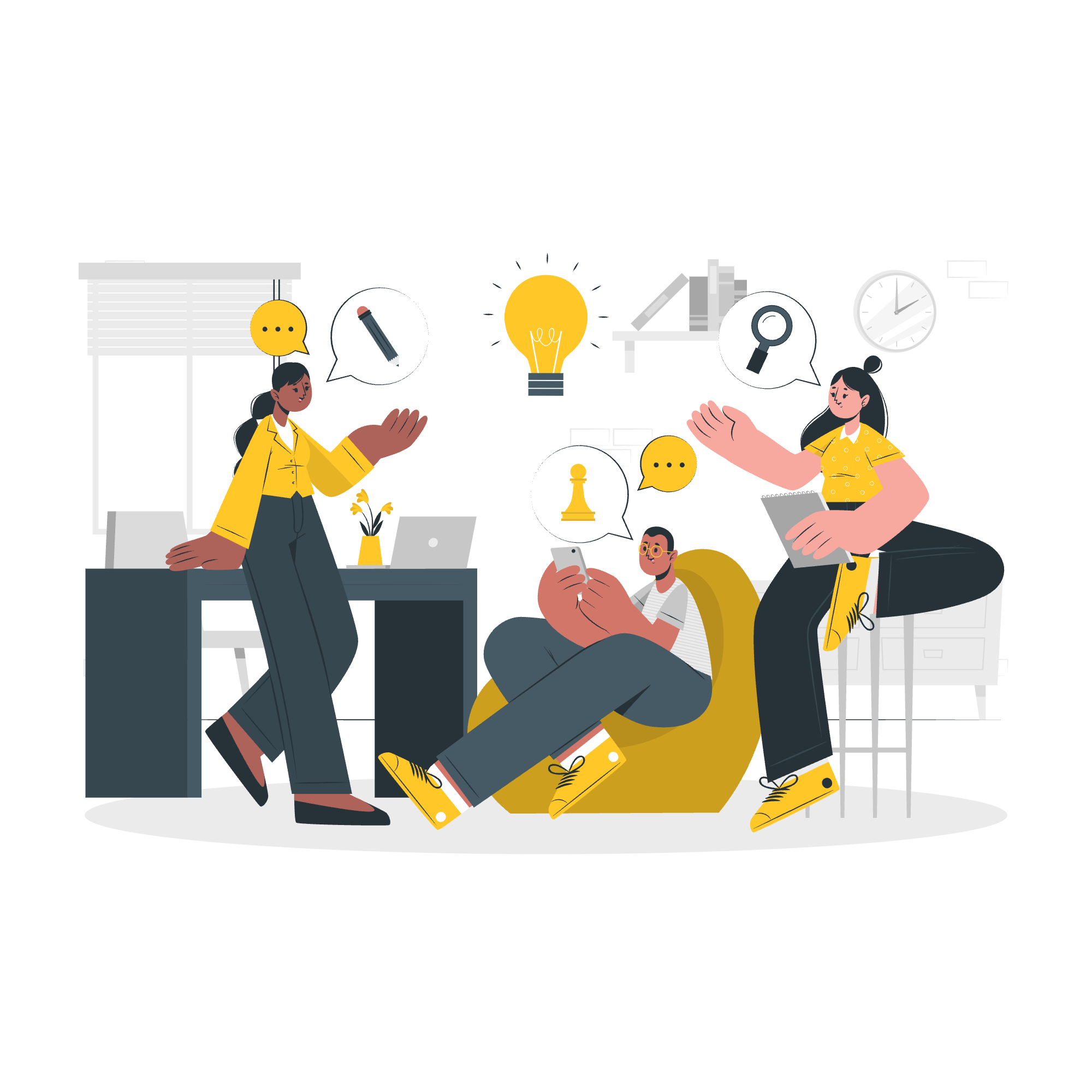
ニーズとシーズを効果的に結びつけるためには、体系的なアプローチが必要です。
デザイン思考のフレームワークを活用することで、両者の接点を見つけやすくなります。
まず、共感フェーズで顧客の課題を深く理解し、定義フェーズで解決すべき問題を明確化します。
次に、発想フェーズで保有技術との組み合わせを検討し、試作フェーズで実現可能性を検証します。
具体的には、「技術マッピング」という手法が有効です。
縦軸に顧客ニーズ、横軸に保有技術を配置し、交差点で新しい商品アイデアを発見します。
例えば、「高齢者の安全確保」というニーズと「IoTセンサー技術」を組み合わせることで、見守りサービスのアイデアが生まれます。
また、オープンイノベーションの活用も効果的です。
外部の技術やアイデアを取り込むことで、自社のシーズだけでは解決できなかったニーズにも対応可能になります。
実際の企業事例を通じて、ニーズ志向とシーズ志向がどのように成功につながったかを詳しく見ていきましょう。
市場ニーズから出発した事例と技術起点で革新を起こした事例を比較することで、それぞれのアプローチの効果的な活用法が理解できます。
トヨタのプリウスは、環境への配慮と燃費向上という市場ニーズを的確に捉えた成功例です。
消費者の環境意識の高まりという社会的ニーズに対し、ハイブリッド技術で応えました。
ダイソンの掃除機開発も、「吸引力が持続する掃除機」という明確なニーズから始まりました。
従来品の「吸引力低下」という課題を、サイクロン技術で解決し、市場を革新しました。
これらの事例に共通するのは、顧客の潜在的な不満を詳細に分析し、それを解決する技術を開発・改良した点です。
市場調査や顧客フィードバックを重視し、継続的な改善を行っています。
3Mのポスト・イットは、接着力の弱い糊という「失敗作」から生まれた典型的なシーズ主導の成功例です。
当初は用途が不明でしたが、「一時的に貼れるメモ」というニーズとマッチしました。
ソニーのウォークマンも、「小型化技術」と「音楽を持ち歩く」というライフスタイルの変化を結びつけた革新的な商品です。
技術的優位性を活かして新しい市場を創造しました。
これらの成功要因は、技術の可能性を広い視野で検討し、従来にない用途や市場を開拓した点にあります。
また、初期の市場反応を注意深く観察し、商品を改良していく姿勢も重要でした。
ニーズ・シーズ・ウォンツの理解不足から生じる失敗パターンを把握することで、リスクを回避できます。
技術偏重や市場軽視が主な失敗原因です。
技術志向の企業でよく見られるのが、「優れた技術だから売れるはず」という思い込みです。
しかし、技術的優位性だけでは市場での成功は保証されません。
顧客のニーズや使用場面を十分に検討せずに商品化すると、市場に受け入れられないリスクがあります。
逆に、ニーズ重視でも「表面的な要求」にとらわれすぎると、競合との差別化が困難になります。
例えば、「安い商品が欲しい」というウォンツに対し、単に価格を下げるだけでは持続的な優位性は築けません。
成功のためには、継続的な市場観察と柔軟な戦略修正が不可欠です。
また、社内の技術部門とマーケティング部門の密接な連携により、ニーズとシーズのバランスを保つことが重要です。


ニーズ・シーズ・ウォンツの理解は、成功する商品開発の基礎となります。
顧客の課題(ニーズ)と技術的可能性(シーズ)、そして具体的な要求(ウォンツ)を適切に組み合わせることで、市場に受け入れられる革新的な商品が生まれます。
重要なのは、どちらか一方に偏るのではなく、バランスの取れたアプローチを心がけることです。
今後の事業戦略において、これらの概念を活用し、顧客満足と技術革新の両立を目指してください。
弊社、株式会社アイデアプラスはお客様が抱える課題を一緒に考え、クリエイティブの力で課題解決・目標達成に向けて伴走いたします。
ニーズやシーズの分析・活用についてお困りの際は、ぜひ株式会社アイデアプラスにお気軽にご相談ください。